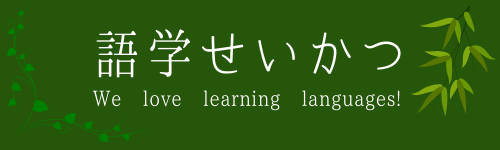もう相当前のことになりますが、高校生のときに勉強嫌いだったし進学校でもなく友人との話にも大学進学や進路について具体的な話をすることもなく過ごしていました。
それが高校3年になって急にこのままじゃいけないと思ったんです。はっきりしたことは忘れましたが、一つだけ覚えているのは「スポーツも勉強も特にできる訳でなく特技がある訳でもない自分がこの先どうやって生きていくのか・・・できるとすれば一番できるのは勉強かな」と、そんな風に焦りのようなものがあったんです。
幸い英語は好きでした。点数が高いわけではなかったけど好きでした。
そして志望は自然に私学文系になったので、英語が好きな自分にはあとは集中して詰め込んでいけばどうにかなった訳で、浪人もしたので集中して詰め込み学習をしていわゆる関関同立に入れた訳です。
それが中学生ぐらいから数学が苦手なのか・・嫌いだったんです。その年齢のころ特に「きちんとする」ことがすごく苦手だったんです。だから計算をきちんと積み重ねて解答を出すということが苦痛にも近い感じでした。
ただ解き方さえ理解したらできないこともなかった記憶があります、ただ嫌いでした。
そこで、タイトルにも書いた「素朴な疑問」なんですが、例えば今日は3時間勉強しましょうとなったとき。
英語や歴史等であれば3時間は集中さえできれば3時間分の勉強になるじゃないですか。
それが数学や物理なんかの場合、3時間でも解き方を考える時間があって、解き方が分からなくて考える場合は3時間でも全然進まない可能性があるじゃないですか。
3時間のうち2時間は考えることに費やしました。ましてや3時間かけて解答が見つかりませんでした、となった場合に今日は「3時間勉強したぞ」という気持ちになるのか。
おそらく〇十分考えて解けなければ解答方法を見るなどで折り合いをつけているんでしょうが、数学を受験勉強したことがないのでそこが分かりません。
誤解なきよう、「考えること」自体に意義はあるとは思っています。
ただ素朴な疑問なんです。
’25 1/28 勉強時間について素朴な疑問
 雑記
雑記